
こんにちは。
この記事では、軽度知的障害と自閉スペクトラム症(ASD)、ADHDを併せ持つ息子、そしてそのきょうだい児(妹)を育ててきた私の体験をまとめています。
就職して落ち着いてきた今、ようやくこれまでのことを振り返ることができるようになりました。
出産と育児のスタート——想定外の始まり
正直、障害児育児が自分に訪れるとはまったく想像していませんでした。
赤ちゃんとの初対面は感動の瞬間。
…のはずが、実際には動かず、固まったままの息子の姿。
「生きていてくれるだけでいい」——そう感じる毎日が始まりました。
NICUと緊急搬送——孤独なスタートライン
生後間もなく、息子は救急搬送からのNICU入院へ。
不安しかない日々の中で、誰にも相談できず、
「おめでとう」の言葉すら、正直つらく感じてしまいました。
幸せを噛み締める時間など、まったくなかったのが現実です。
寝ない・泣き止まない日々とご近所への配慮

寝つきが悪く、夜通し泣き続ける息子。
ご近所のことも気になって、夜間ドライブで気を紛らわせる日々が続きました。
母乳をがむしゃらに飲み続けて心配し保健師さんに相談したところ、「いくら飲んでも大丈夫」と言われましたが、8ヶ月で体重11キロ…。筋力がついていないため、まるでマシュマロマンのようでした。
お散歩では周囲の視線が気になり、自然と早足に…
「様子見」と「お母さんのせい」
定期検診では、何を言っても「様子を見ましょう」と言われるばかり。
言葉にはされないけれど、全て**「お母さんの育て方のせい」**と責められているような気がしていました。
家庭内でも、行き場のない孤独感

いつから障害児育児だったのかもわからないまま、
とにかく「走り続ける」感覚でした。
親にしか心を開けず、家族間もギスギスし、
夫ともたびたび衝突。ついには家を飛び出したこともありました(でもすぐ帰宅…)。
支援センターや専門機関——違和感と孤独
地域の支援センターでも、やはり違いを感じるばかり。
それでも専門機関では「様子見」…。
周囲と比べてしまう自分に苦しみつつ、
「いいところ探し」ができる自分になりたかった。
立ち上がるきっかけ——「頼る」ことの大切さ

「全部私の責任」と感じて、
息子にも周囲にも、いつも「ごめんなさい」と思っていました。
でも少しずつ、
- 頼れる人には頼る勇気
- 制度やサポートを知る努力
- 吐き出せる相手を見つける工夫
を意識することで、少し心が軽くなった気がします。
私にとっての転機——仕事への復帰
一番大きかったのは、仕事に復帰したことです。
保育園に預けて正職員として働くことで、
ふたりきりの世界から視野がぐんと広がりました。
- 1日の半分を仕事で切り替え
- 残り半分を「親」として全力で向き合う。
そのバランスが、心を健康に保つ鍵になりました。
金銭面でも将来の不安が軽くなり、
保育園も、グレーゾーンの子どもに理解のある園が地域にはありました(※自治体ごとに異なるので要確認)。
ただ、放課後等デイサービスは当時の私は全く知らず、利用していませんでした…
放課後当デイサービスについての記事はこちら:【グレーゾーンでも申請OK?】療育手帳と特別児童扶養手当・放課後等デイサービスまで
きょうだい児の誕生と気づき

その後、娘(きょうだい児)が誕生しました。
彼女の子育ては、今までとは全く違いました。
寝て、笑って、成長していく姿がこんなにも穏やかで楽しいものだとは…。
そんな中、ふと思ったのです。
「私が安定しているから、子どもたちも落ち着いているのかも」と。
息子の頑張りが、あらためて見えてきました。
「こんなに頑張っていたんだ。ちゃんと認めてあげなくちゃ」と。
きょうだい児の心のケアも忘れずに
「きょうだい児」は、障害や医療的ケアが必要な兄弟姉妹を持つ子どもです。
娘にはきっと、次のような気持ちを感じさせてきたかもしれません:
- 寂しさや疎外感
- 自分の感情を抑える癖(本当はもっと甘えたかったと言います…)
- 「いい子」でいようとするプレッシャー
- 将来への不安(介護など)
それでも、彼女の存在は私にとって子育ての楽しさを再発見させてくれました。
「生まれてきてくれてありがとう」
心から、そう思います。
関連記事 きょうだい児についてまとめた記事はこちらから:軽度知的障害の兄とその妹・きょうだい児について|障害児育児の課題点と体験談
最後に——情報がある社会へ

今回の記事では、障害をもつ子どもを育てる親の視点からお話ししました。
育児は一人ひとり違います。
だからこそ、情報が届きやすい社会になってほしいと願っています。
知らないことで悩み、苦しむ親御さんが増えませんように。
そして、親だけが責任を負わされる社会ではなくなるように。
私の経験の中で知ることのできた制度や情報はブログ内で綴っています。よかったら覗いてみてください🌱
話すだけでも、心は軽くなります。
どんなことでも、コメントいただけたら嬉しいです。
明日も心まるく・穏やかに過ごしていくことができますように🌈
執筆者プロフィール
障害のある息子を育てながら、日々の支援・工夫・制度利用について情報を発信しています。専門家ではありませんが、同じ悩みを抱える方のヒントになればと願っています。

関連記事✨
【体験談】軽度知的障害の息子が1泊2日のグループホームへ!自立への第一歩
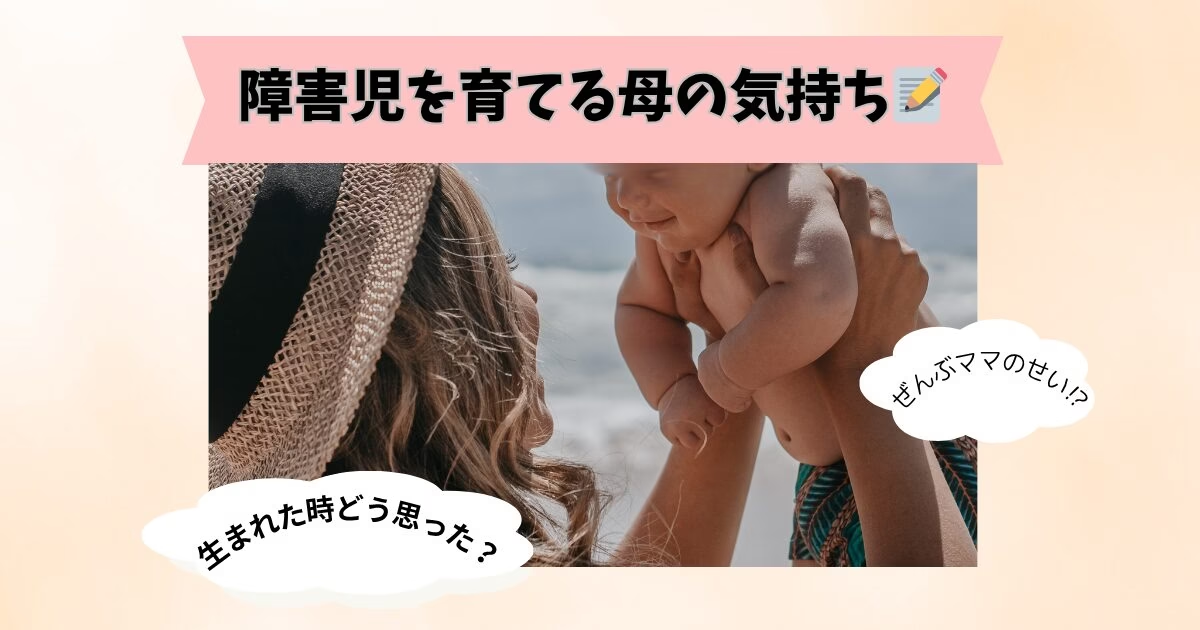
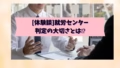
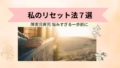
コメント