
こんにちは。
現在、我が家の息子は特例子会社の障害者雇用枠で働いています。就労してから4年目を迎えました。
ここまで継続できたこと自体がとても嬉しいことなのですが、実はこれまで「もう無理かもしれない…」と思う場面が何度もありました。
今日はその経験を振り返りながら、家庭でどのような対応をしてきたか、そして支援機関とどう連携してきたかについて、まとめてみたいと思います。
息子の障害特性と抱えていた困りごと
息子には以下のような診断があります。
- 自閉症スペクトラム(ASD)
- ADHD(注意欠如・多動症)
- 軽度知的障害
いずれも見た目では分かりにくい障害で、本人の努力ではどうにもならない“生きづらさ”を感じやすいものです。
就労後も、不安や体調不良が繰り返されることがありました。
現れた不調
- 円形脱毛症
- 腹痛や嘔吐などの身体症状
- 睡眠の質の低下や食欲不振
心と体はつながっていて、特に発達障害のある子にとっては、環境から受けるストレスがすぐに身体症状として出てしまうことが少なくありません。
不安の背景にあったこと
息子が「会社に行きたくない」「吐き気がする」と訴える日が続いた時、背景には以下のような悩みが隠れていました。
- 仕事の内容が難しくてついていけない
- 同僚とのコミュニケーションが苦手
- 期待される仕事に応えられない自分への落ち込み
- 給料や生活費への不安(お金の使い方)
加えて、「スマホを通じた人間関係」や「職場の空気をうまく読めないことへのストレス」など、本人がうまく言語化できない“見えない負担”が積み重なっていたのだと思います。
家庭でできたこと・行った対応

我が家では、できる限り以下のようなことを意識して対応してきました。
✔️ 話を聴ける環境づくり
まずは、本人が「つらい」と言える雰囲気を家庭で作るように心がけました。
頭ごなしに叱るのではなく、“不安の理由”に目を向けることが最も大切です。
✔️ 気分転換や休息の提案
調子が悪い時は無理をせず、散歩に出かけたり、気持ちの切り替えができるような工夫をしました。
✔️ 主治医への相談
症状が強く出ているときは、すぐに主治医へ相談。
精神的・身体的なサポートの視点からもアドバイスを受けました。
✔️ 有給休暇や短時間勤務の調整
会社と連携を取りながら、1ヶ月半の時短勤務も経験。
その間、体力と心を回復する時間になりました。
✔️ 就労支援センターとの連携
第三者として信頼できる支援員さんを介して、職場に悩みを共有。
会社との橋渡しになっていただくことで、直接伝えにくいことも調整できました。
特例子会社での配慮とありがたさ

息子のように、軽度の知的障害がある場合、「できてしまう」行動も多く、周囲から見れば困りごとが見えにくい部分があります。
たとえば急に「一人暮らしがしたい」「マイナンバーカードはどこにある?」など、思い立って行動してしまうことも。行動できてしまう=判断が正しいわけではないため、周囲の大人の見守りが不可欠です。
そんな中、職場では仕事内容が難しいときには配置転換の配慮をしてくださり、息子も「わかる・できる」安心感を取り戻すことができました。
これまで多くの障害者雇用を支えてきた特例子会社の対応力には、本当に助けられたと感じています。
家庭でも工夫は続く
仕事と体調は密接につながっているため、家でのサポートも継続が必要です。
- 偏食傾向があるので、喉を通りやすい食事を工夫
- 洋服や素材のこだわりが強いので、ストレスにならない服選び
- 就寝時間や朝のルーティンの見直し など
本人が安心できる“日常の土台”を支えるのが家庭の役割だと感じています。
転職も視野に…でも今は「安心」が優先
しんどさが続いたとき、私たちも「転職」の選択肢を考えました。
でも最終的に、「今の職場で配慮してもらえている」ことと、「今の状態で新しい環境に入ることのリスク」を比較し、当面は継続することを選びました。
「軽度」だからこそ、できることも多い。
でもだからこそ、見えない支援の必要性に気づくのに時間がかかることもあります。
最後に
どんなに配慮された職場でも、障害がある子どもが就労を継続するのは簡単なことではありません。
けれど、周囲の理解と、家庭・支援機関との連携があれば続けられることもあります。
本人の声に耳を傾けながら、これからも「無理せず、でも一歩ずつ」前に進んでいけたらと思っています。
※執筆者プロフィール:
障害の息子を育てる母として、日々の支援や社会参加に向けた体験を発信しています。専門家ではありませんが、実体験を通して、同じ悩みを抱える方の力になれたらと願っています。
▶️Instagramもしています。よかったらこちらから覗きにきてください🌱
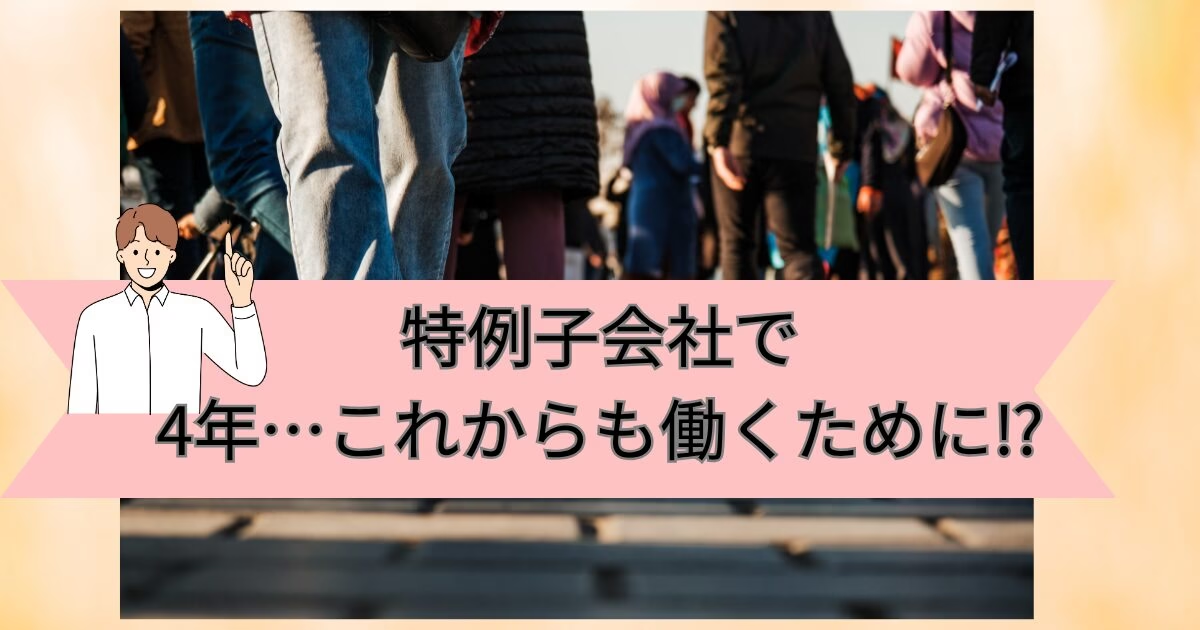


コメント