【発達グレーゾーンの支援制度まとめ】特別児童扶養手当・療育手帳・放課後等デイサービスを実体験で解説

「うちの子は軽度だから」「支援の対象外だと思っていた」──そんな私が、実際に支援制度を受けられた体験をもとに、療育手帳の取得、特別児童扶養手当、放課後等デイサービスの利用についてわかりやすく解説します。
まさか対象になるとは思わなかった我が子と支援制度との出会い
息子は「発達グレーゾーン」と言われ、最初は療育手帳も取得できませんでした。そのため、支援制度の対象外だと思い込んでいました。
しかし、小学校に入り様々な困りごとが明確になる中で、改めて支援制度の情報を調べ、少しずつ制度を活用できるようになりました。
このページでは、以下のような悩みを持つ方に向けて情報をまとめています:
- 療育手帳の取得方法を知りたい
- 特別児童扶養手当の条件や申請方法が知りたい
- 放課後等デイサービスって何?どうやって使うの?
療育手帳取得から始まった支援の第一歩
最初に取得を目指したのが療育手帳です。軽度知的障害の診断を受けたことで、再度判定を申し込み、取得することができました。
詳細な流れは別記事で解説しています:
軽度知的障害の診断後に取るべき3つのステップ|療育手帳交付までの母親の体験談
特別児童扶養手当の条件と申請方法
当時の私は、この制度が我が子にも対象となるとは全く思っていませんでした。
制度の概要
特別児童扶養手当は、20歳未満の障害のある子どもを養育している家庭が対象です。
- 対象:20歳未満の障害児を養育する保護者
- 支給額(令和6年4月以降):
- 1級:55,350円/月
- 2級:36,860円/月
- 申請に必要なもの:医師の診断書、市区町村の申請書類など
- 所得制限:世帯主の所得で判定(共働きでも対象になる場合あり)
我が家の申請フロー
- 市役所の福祉課で申請書類を受け取る
- 主治医に診断書を依頼(数日〜1週間)
- 必要書類を揃えて提出
- 審査結果を待つ(1〜2ヶ月ほど)
- 支給決定後は定期的に更新手続きが必要
申請時に気をつけたポイント
大事なのは「できること」よりも「日常で困っていること」を具体的に伝えることです。
我が家が伝えた内容の一部:
- 髪を洗うのが苦手(なで洗いしかできない)
- 体調不良を言葉で伝えられない
- 季節に合わない服を選ぶ
- 極端な偏食がある
- 予定変更に強い不安が出る
放課後等デイサービスを使わなかったことを今でも後悔

療育手帳を取得した後も、「放課後等デイサービス」という制度の存在を知らず、利用しないまま数年が過ぎてしまいました。
当時これを知っていれば、共働きの私たちも、もっと安心して仕事と子育ての両立ができたと思っています。
放課後等デイサービスとは?
- 対象年齢:6歳〜18歳(場合により20歳まで)
- 自己負担:原則1割(残りは自治体負担)
- 支援内容:日常生活支援・学習支援・レクリエーションなど
- 対応施設:平日・休日ともに対応している施設もあり
▶ 厚生労働省|放課後等デイサービスとは
WISCなどの検査結果があると、利用相談がスムーズに進む場合もあります。
施設によって雰囲気や支援の質が大きく異なるため、必ず複数の事業所を見学することをおすすめします。
まとめ|支援制度は「知らなければ受けられない」からこそ、まずは行動を
支援制度や障害の特性は一人ひとり違います。
「うちは関係ないかも…」と思っても、まずは自治体や専門機関に相談してみることが第一歩です。
手続きはたしかに手間がかかりますが、受けられる支援は想像以上に大きいこともあります。
この体験が、誰かの不安を少しでも和らげ、行動のきっかけになれば嬉しいです。
※この記事は筆者の体験に基づいており、制度の詳細や変更については必ず自治体や厚労省の公式情報をご確認ください。
※執筆者プロフィール:障害の息子を育てる母として、日々の支援や社会参加に向けた体験を発信しています。専門家ではありませんが、実体験を通して、同じ悩みを抱える方の力になれたらと願っています。
▶️Instagramもしています。よかったらこちらから覗きにきてください🌱
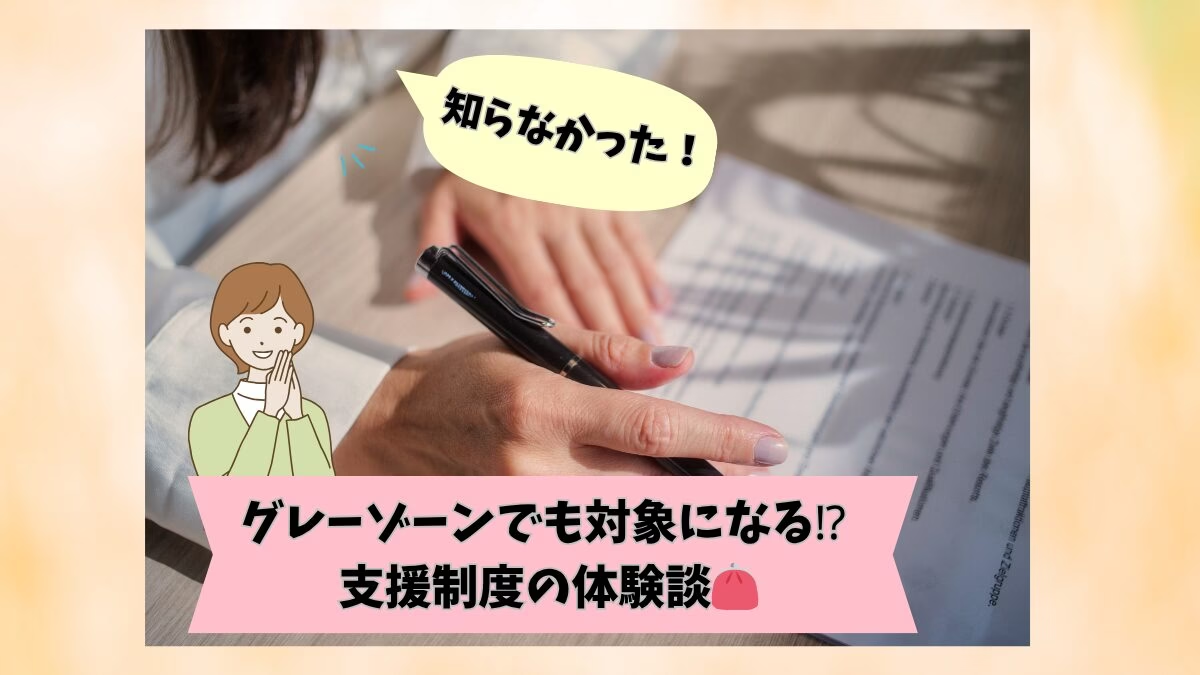
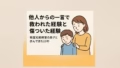


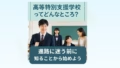



コメント