はじめに
軽度知的障害のある息子と、健常児の妹。
小さいころから一緒に育ってきた2人の関係は、特別でありながら、とても「普通の兄妹」でもあります。
障害があるからといって、いつも穏やかに仲良くしているわけではありません。
むしろ日常には小さなケンカが絶えず、そのたびに涙や怒りがぶつかり合いました。
けれど、ケンカの先には必ず「仲直り」がありました。
それが2人の関係を少しずつ強くし、今の信頼関係につながっています。
今日は、わが家でよくあった「ケンカと仲直りのパターン」をご紹介します。
同じように兄妹を育てている方のヒントになれば嬉しいです。
ケンカのよくある原因
① 順番をめぐる争い
テレビゲームの順番、お風呂に入る順番、好きなお菓子を食べる順番…。
「僕が先!」「私が先!」と、順番をめぐるケンカは日常茶飯事でした。
特に息子は「順番を守ること」にこだわりが強く、妹がルールを少しでも崩すと怒りが爆発。
一方の妹は「どうしてそんなにこだわるの?」と納得できず、すぐに反発していました。
② 言葉の行き違い
息子は軽度知的障害のため、言葉でうまく気持ちを伝えるのが難しいときがあります。
本人としては「貸して」と言いたかっただけなのに、表現が強すぎて妹には「命令された」と感じられてしまうことも。
その結果、「イヤ!」「なんでお兄ちゃんなの!」とケンカに発展しました。
③ 妹の“我慢の限界”
普段から兄を優先する場面が多いせいか、妹の我慢が積み重なって爆発することもありました。
「どうしてお兄ちゃんばっかり!」と泣き出す姿を見ると、胸が痛みました。
このとき私が気づかされたのは、妹にも「聞いてほしい気持ち」「認めてほしい気持ち」があるということ。きょうだい児とされ、彼女への対応についても難しさを感じました。
兄へのサポートに目が向きすぎると、妹の心がすり減ってしまうのだと実感しました。
仲直りのパターン集

パターン① 「母が翻訳者になる」
息子の気持ちを私が言葉にして妹に伝えたり、妹の怒りを息子にわかりやすく説明したり。
“翻訳者”になることで、お互いの誤解が解けて落ち着くことがよくありました。
たとえば――
息子:「〇〇〜(名前)💢」
妹:「だって、そんな言い方嫌だ!」
私:「お兄ちゃんは“やめてほしい”って伝えたかっただけなんだよ」
すると妹は「そうなの?」と受け入れやすくなり、ケンカが和らぎました。
パターン② 「時間が解決」
どんなに言葉で仲裁しても、お互い怒りでいっぱいのときは話が通じません。
そんなときはあえて別々の部屋にして、時間をおきます。
しばらくすると、息子の方から「もういいよ」と歩み寄ったり、妹が「さっきはごめん」と素直に謝ったり。
時間の力は思った以上に大きかったです。
パターン③ 「笑いで仲直り」
一緒にテレビを観て、ふと大笑い。笑いのツボは似ているようです。
怒っていた妹もそこから一気に仲直り。
不思議なことに、2人の間では“笑い”が仲直りの近道になることが多かったです。
親が無理に「仲直りしなさい」と言うよりも、自然に笑い合う方が効果的でした。
親としての気づき
妹へのケアも忘れない
「障害がある兄を支える」ことばかり考えていた私ですが、妹にも同じくらい気持ちを注ぐ必要があると学びました。
「二人とも大事だよ」と伝える時間を持つことで、妹は少しずつ素直に兄を受け入れられるようになった気がします。
ケンカは悪いことではない
最初は「ケンカをなくしたい」と思っていました。
でも、ケンカを通して学ぶことも多いのだと気づきました。
・相手の気持ちを考える
・自分の感情をコントロールする
・仲直りする方法を見つける
こうした経験は、兄にも妹にも大切な学びになっていました。
成長しても変わらないこと
2人とも成人に近づいた今でも、ちょっとした言い合いは続いています。
けれど、ケンカのあとに必ず仲直りできる関係は変わっていません。
妹が「お兄ちゃんはどうするの?」といつも気遣ってくれとき、私は胸がいっぱいになります。
兄妹の関係は不器用でも、確かに絆が深まっているのだと感じます。
まとめ 🌈
軽度知的障害のある兄と健常児の妹。
ケンカと仲直りを繰り返してきた日々は、決して平坦ではありませんでした。
でもそのたびに、2人は「相手を理解すること」「許すこと」「歩み寄ること」を学んできました。
そして、親である私自身も「子ども同士の力を信じること」を学びました。
兄妹の関係は、きれいごとばかりではありません。
けれど、ぶつかり合いも含めて「大切な宝物」だと、今では思えるのです。
🌱プロフィール
障害のある息子を育てながら、日々の支援・工夫・制度利用について情報を発信しています。
専門家ではありませんが、同じ悩みを抱える方のヒントになればと願っています。
インスタはこちらから🌱
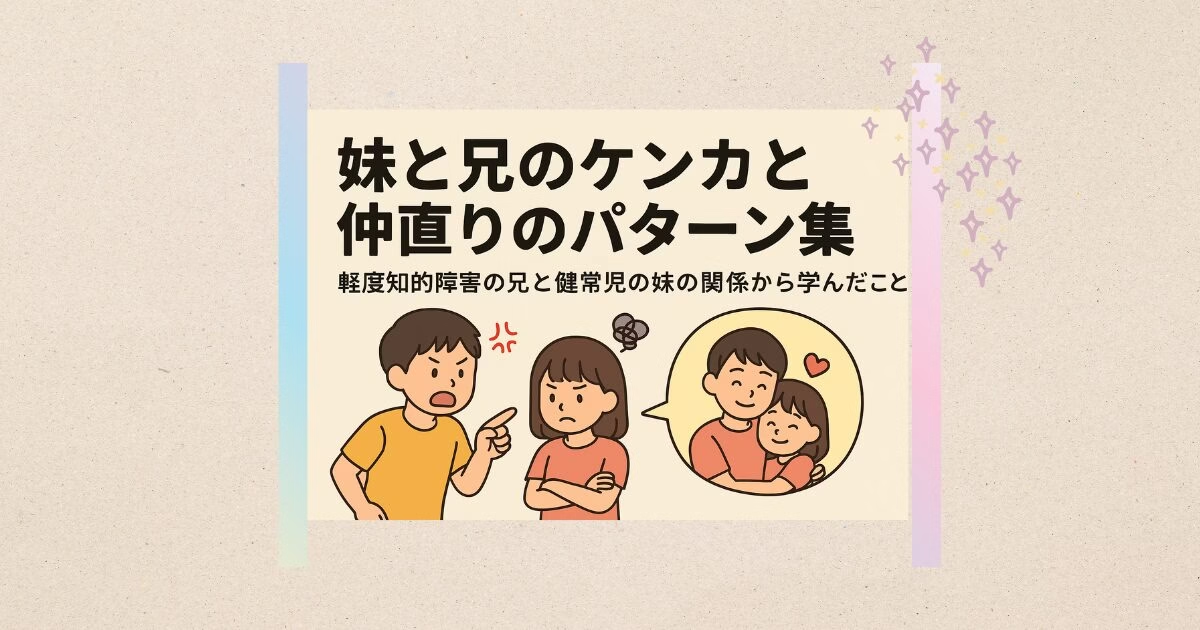

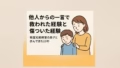
コメント