「特別支援学校ってどんな場所?」
「子どもが進学するかもしれないけれど、正直よくわからない…」
そんな不安や疑問を抱えている保護者の方も多いと思います。
私自身も、最初は「支援学校」と聞いてもまったくイメージが湧かず、どこか**隔離された静かな場所なのかな?**という偏った印象を持っていました。
でも、実際に息子が高等特別支援学校に通ってみて、その考えはガラリと変わりました。
この記事では、実際に通ったからこそわかる特別支援学校のリアルな様子を、保護者の視点からお伝えします。
高等特別支援学校とは?
高等特別支援学校は、主に軽度~中等度の知的障害や発達障害のあるお子さんが通う就労を見据えた特別支援教育の場です。
息子が通っていた学校では、療育手帳の取得を条件とすることもあり、障害の特性や程度に応じたサポート体制が整っていました。
学校によって方針や支援の内容は異なりますが、息子の通った学校は、一般企業への就職(障害者雇用)を目指すことが大きな目的となっていました。
実習と就労支援が1年生から始まる
特別支援学校では、1年生の早い段階から職場実習が始まります。息子の学校でも、以下のような実践的な学びが日常的にありました:
- あいさつや自己紹介の練習
- 企業訪問時のマナー指導
- お礼状の書き方
- 作業や報告の仕方など
また、個々の特性や希望に応じて実習先を決定し、企業と連携しながら進めるという丁寧なサポート体制もありました。
親としても、「この子にはどんな仕事が合っているのか」「通勤可能な範囲にある企業は?」といった、将来への視野が自然と広がる貴重な期間でした。
実習先の選定で大切にしたこと
正直に言うと、「障害があるからといって、どこでも働けるわけではない」と痛感しました。
実際の仕事には、求められる作業レベルと本人の特性の間にギャップがあることもありました。
私たちは、“ずっと続けられること”を優先し、ハードルが高すぎる実習先は選ばないようにしました。
就労支援の先生と何度も話し合い、企業側のニーズと息子の強みが一致したところを何度か実習。本人にとっても達成感を持って取り組めるような職場とのご縁を大切にしました。
学校行事や部活動も充実!友達との時間も

「特別支援学校=勉強だけの静かな場所」ではありません。
むしろ、行事や部活動、学校生活もとても活発で充実していました。
- 修学旅行
- 体育祭・文化祭
- 英検や運動大会での表彰
- 外出イベントや友達との交流
運動部・文化部ともに活動があり、将来に役立ちそうな趣味や技能に触れる機会もたくさんありました。
「学ぶことが楽しい」と感じられる環境が整っていると実感しました。
感情の波への対応と家庭でのサポート
中には、感情的になってしまうお子さんもいる場面がありました。
そうした状況に接すると、息子自身も戸惑ったり、嫌な気持ちになったりすることも。
その都度、家庭で「どう受け止めるか」「どう対応するか」を一緒に話し合い、学びの機会にしていきました。
特別支援学校では、子ども自身だけでなく、家族にも成長の機会が与えられる場所だと感じました。
交通費の支援制度も活用
実は、特別支援学校に通う生徒には交通費の補助制度がある自治体も多く、申請によって通学の負担がかなり軽減されました。(我が家の場合、通学用の定期代は全て補助していただくことができました)
経済的な理由で選択肢を狭めずに済んだのは、大きなメリットでした。
学校見学は“フィーリング”も大切に
同じ「高等特別支援学校」でも、学校によって雰囲気や方針、教職員の姿勢は大きく異なります。
私たちも数校見学をし、「ここなら通わせたい」と思える場所を選びました。
- 校舎の清潔さや設備(冷暖房など)
- 教室や廊下の雰囲気
- 生徒たちの様子や先生の対応
実際に足を運ぶことで、ネットではわからない部分も見えてきます。
「ここなら大丈夫」と思える学校との出会いは、子どもの安心感と成長につながる大切な第一歩です。
📄【学校見学チェックリスト(高等特別支援学校用)】
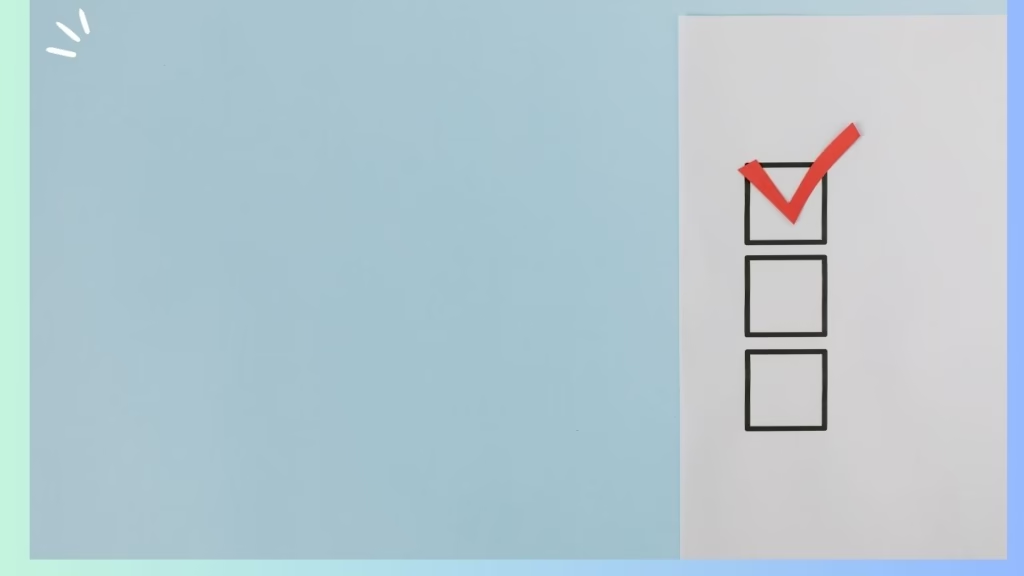
1. 基本情報
- □ 学校の設立目的・対象の障害種別を明確に説明してもらえた
- □ 療育手帳の有無や入学条件などの説明があった
2. 教育内容と進路支援
- □ 実習の頻度や内容、企業連携について確認できた
- □ 就職以外の進路(福祉就労・進学など)についても説明があった
- □ 就労支援専門の先生がいるか確認できた
3. 校内の雰囲気
- □ 教室や廊下が清潔で明るい雰囲気だった
- □ 生徒が楽しそうに過ごしている様子が見られた
- □ 教職員の対応が丁寧・穏やかだった(これがやはり決め手になりました!)
4. 行事・課外活動
- □ 体育祭や文化祭などの行事が開催されている
- □ 部活動や放課後活動について説明を受けた
5. 通学と環境面
- □ 自宅からの通学方法や交通費の支援制度について確認
- □ エアコンなどの設備、トイレの清潔さなども確認
6. 保護者との連携
- □ 面談の頻度や連絡方法について説明があった
- □ 親の相談対応(カウンセリング・進路相談)体制がある
7. その他
- □ 見学時に生徒の実習や授業の様子を見られた
- □ 「この子に合いそう」という感覚が持てた
✔ 見学後は、保護者自身の第一印象も大切にしましょう。
まとめ:進路に悩む前に、まず“知ること”から始めよう
特別支援学校に対して不安があった私ですが、今では「この学校でよかった」と心から思っています。
高等特別支援学校は、“障害のある子が働くために必要な力”を親子で一緒に育てていく場所。
そして、ただ「就職を目指す」だけでなく、日々の学校生活の中で自信・人間関係・社会性を育む大切な場所でもありました。
もし、お子さんの将来について悩まれている方がいたら、ぜひ一度、地域の特別支援学校の見学に足を運んでみてください。
きっと、「あ、ここならこの子に合うかも」と思える場所が見つかるはずです。
※本記事は個人の体験に基づいています。進路選びや支援内容については、必ず各自治体・学校・専門機関に確認してください。
🌱プロフィール
障害のある息子を育てながら、日々の支援・工夫・制度利用について情報を発信しています。専門家ではありませんが、同じ悩みを抱える方のヒントになればと願っています。

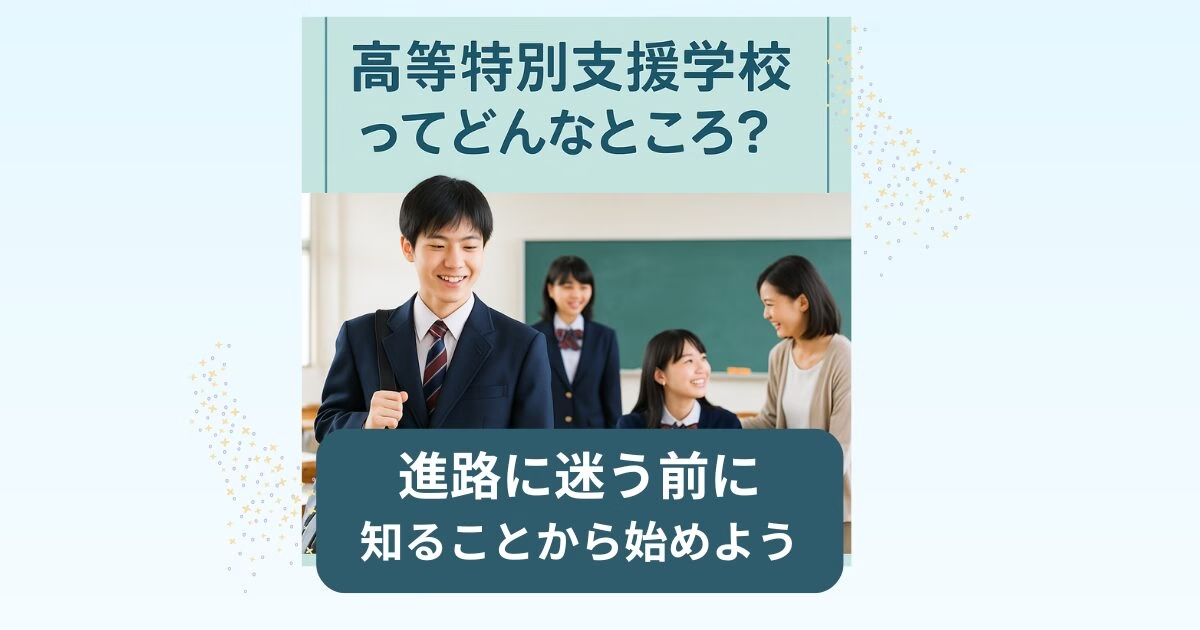

コメント