はじめに

「また保育園から呼び出し…」「今日、仕事どうしよう?」
そんな不安、共働き家庭なら一度は経験しているはずです。私自身も保育士として20年以上働いてきた中で、何度も保護者の困りごとに直面してきました。
この記事では、**急な発熱や呼び出しに備えるために“今すぐできる準備”**と、実際に使える7つの選択肢をご紹介します。
1. 病児保育サービス(自治体・民間)
急な体調不良でも頼れる心強い味方です。
- 登録制が基本。事前登録は必須!
- 民間:ポピンズ、フローレンス など
- 自治体によっては補助金制度も!
▶ 体験談:
「診断書が必要かどうかなど事前確認しておけば、いざというときスムーズでした。」
2. シッターや家族、ご近所ネットワーク
- 祖父母との預かりルールを明確に
- ママ友との「預かり協定」も有効
- 地域の子育て支援団体も頼れる存在です
3. ファミリー・サポート・センター(通称:ファミサポ)

- 自治体運営で安心・低価格
- 登録すれば、必要なときに依頼可能
- サポート会員との信頼構築がカギ
▶ 地域の活用例:
うちの地域では塾の送迎にも対応。共働きでも習い事が続けられました! お住いの地域の情報誌や市町村のホームページをチェックします。
4. 小児科と連携する訪問型ケアサービス
- 看護師が自宅で対応してくれる安心サービス
- 医療ケアが必要なケースで特に有効
- 首都圏を中心に広がり中。お住いの地域もぜひ検索を!
5. 「子の看護休暇」制度を正しく理解する
- 年間5日(子ども2人以上は10日)取得可能
- 無給扱いが多いが、有給の職場もあり
- 2025年には制度の拡充・柔軟化が義務化へ
▶ 公式サイト確認推奨:
厚生労働省「育児休業制度 特設サイト」
6. どうしても休めないときの乗り切り術
- 日頃から同僚と協力体制を築いておく
- 制度+職場ごとの柔軟対応を相談
- 「家庭でできること」「会社で協力してほしいこと」を書き出しておくのも◎
7. “頼れる人メモ”をスマホに用意しておこう
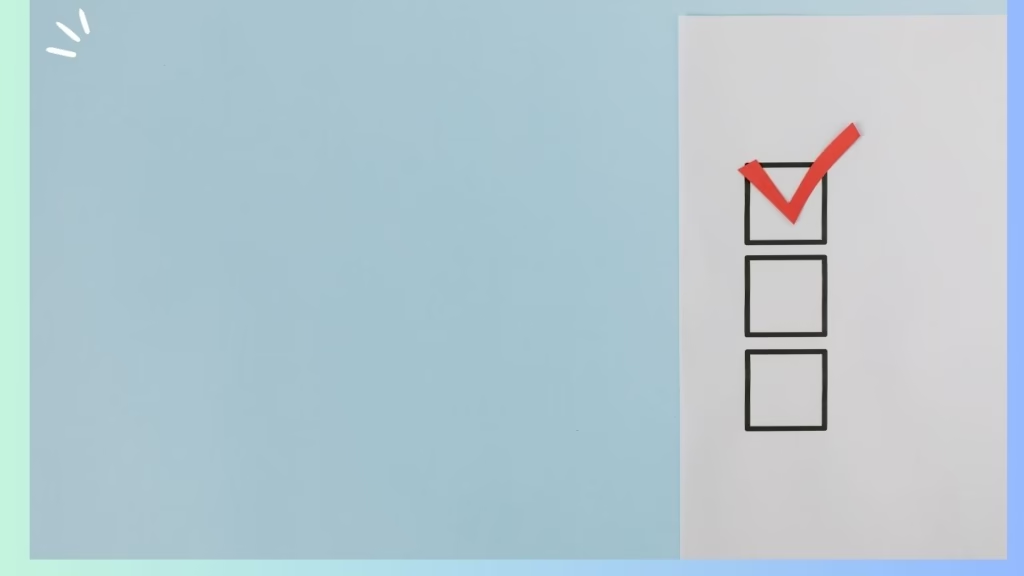
- 病児保育、祖父母、ママ友などの連絡先を常時保存
- 可視化することで、「誰に頼れるか」が明確に!
- 精神的な不安を軽減するためにも有効です
おわりに|「自分を責めない」ことも、立派な選択肢
どれだけ準備していても、予期せぬことは起きます。
そんな時は――
「自分を責めない」
これも大切な“選択肢”です。
あなたは毎日、精一杯頑張っています。
完璧じゃなくてもいい。頼れるものを頼って、家族みんなで乗り越えていきましょう。
あわせて読みたい関連記事✨
✿この記事を書いた人:まる
幼稚園教諭・保育士・放課後児童支援員として、保育に20年以上関わってきた50歳の母です。
家庭では、軽度知的障害のある子どもときょうだい児、2人の子育てに奮闘中。
今回は子育て中の共働きする母親の視点で記事をまとめてみました。
本ブログでは、障害育児のリアルや暮らしの工夫を発信していますが、植物好きの両親の影響で、季節の庭づくりや草花の記録も時々発信中🌷
「同じような境遇の方の心が、少しでもまるくなれば」そんな思いで書いています。
▶️Instagramもしています。よかったらこちらから覗きにきてください🌱


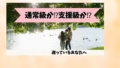
コメント