
はじめに
中学生になった息子が、普通学級での生活に苦しんでいた日々。そんな姿を見て、私たち親子は「本当にこのままでいいのか」と考え始めました。
この記事では、軽度知的障害のグレーゾーンにいた息子が、どのように居場所を見つけ、支援学校という選択肢にたどり着いたかを記録しています。
同じように悩んでいる保護者の方に、少しでもヒントや安心を届けられたら嬉しいです。
1. 中学生時代に感じた現実と親の葛藤
中学の通常学級で、息子は居場所を失っていきました。
苦しそうな顔、成績の厳しさ、バカにされる環境……。
しかし、親として、「まだ普通にできるかも」という思いをなかなか手放せずにいました。
2. 息子の成績と「グレーゾーン」の壁
テストでは暗記科目は平均をとれることもあるけれど、他の教科は赤点すれすれ。
「やればできる」「サボっているだけ」と言われがちなのが、この“グレーゾーン”の難しさです。
でも、「やっていても難しい」…それをわかってあげる役目は私だ、と考えるようになっていきました。
3. 協調性を育んだ部活動との出会い
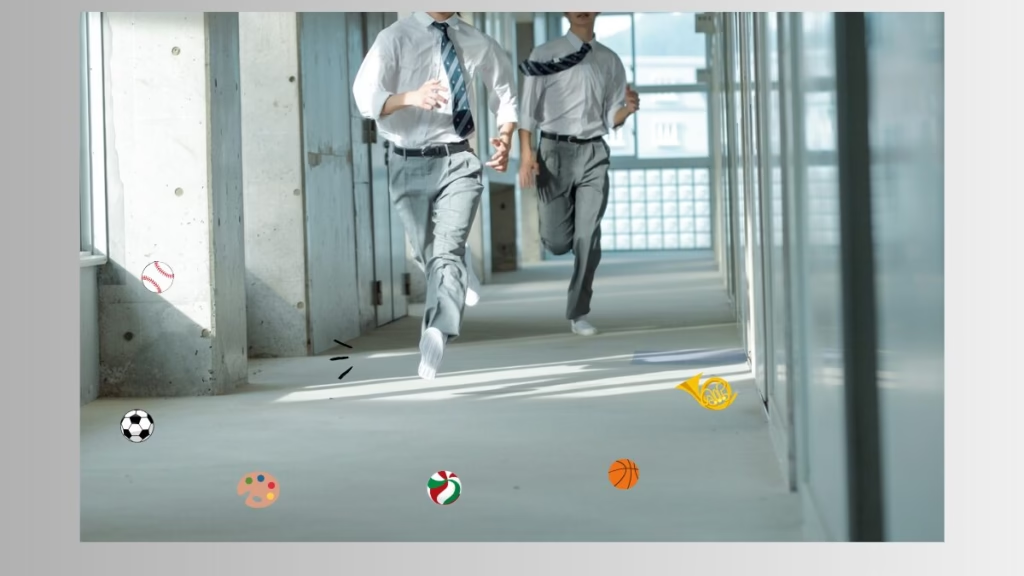
居場所を見つけられたのは、意外にも部活動でした。
上級生や同級生とのやり取りの中で、息子に安心感と達成感が生まれました。
部活動は、支援級のお子さんでも参加できる場合があります。学校に相談してみると、調整が可能な場合もあります。
4. 習い事がくれた自信と得意の発見
ECCで英検4級を取得。文字の暗記やリスニングが得意だった息子には、英語が「できる」と感じられるきっかけに。
スイミングでは4泳法すべてクリアでき、自信につながりました。
こうした本人に合ったものへの挑戦は、軽度知的障害やグレーゾーンの場合でも新たな自信を持つ経験となり貴重でした。
5. 進路を考える:支援学校という選択肢

普通高校だけがすべてじゃない。全日制・通信・支援学校など、選択肢はさまざまです。見学や説明会にもそれぞれ親子で出向きました。
そして、主治医や療育の作業療法士の先生とも相談しながら、最終的に高等特別支援学校への進学を決意しました。高等特別支援学校での生活についてはまた改めてまとめてみたいと思います。
参考資料:文部科学省より高等学校における特別支援教育の 現状と課題について
関連記事:
6. 就労支援を知り、将来への不安が希望に変わるまで
「障害者として生きていく」という現実への葛藤はありました。
でも、高等特別支援学校へ進学したことで就労移行支援や特例子会社の制度を知り、本人に合った支援があることを知ることができました。
また、支援学校では、挨拶やマナーも含めた就労指導を丁寧に受けることができました。そうして、就労への道筋ができ、大きな安心感へつながっていきました。
7. 最後に伝えたいこと
「将来が不安で、仕方がなかった」
そんな気持ちで悩んでいたあの頃の私に、今の息子は教えてくれました。
毎日働きながら「100万円貯めて使うんだ〜」と夢を語る息子。(もちろん凹む時は今尚に大いにありますが😅)
あの頃の心配は、必要な通過点だったのかもしれません。何より親が笑っていることで、安心して生活を送ることができたように思います。お子さんを、ご自身を認めてあげてください。応援しています。
明日も楽しく・心まるく過ごしていくことができますように♪
※あくまで個人の経験に基づいた体験談になります。詳細は専門家、主治医等に相談の上検討してください。
※執筆者プロフィール:障害の息子を育てる母として、日々の支援や社会参加に向けた体験を発信しています。専門家ではありませんが、実体験を通して、同じ悩みを抱える方の力になれたらと願っています。Instagramもやっています。みていただけると嬉しいです🌱
▶️よかったらこちらから覗きにきてください🌱
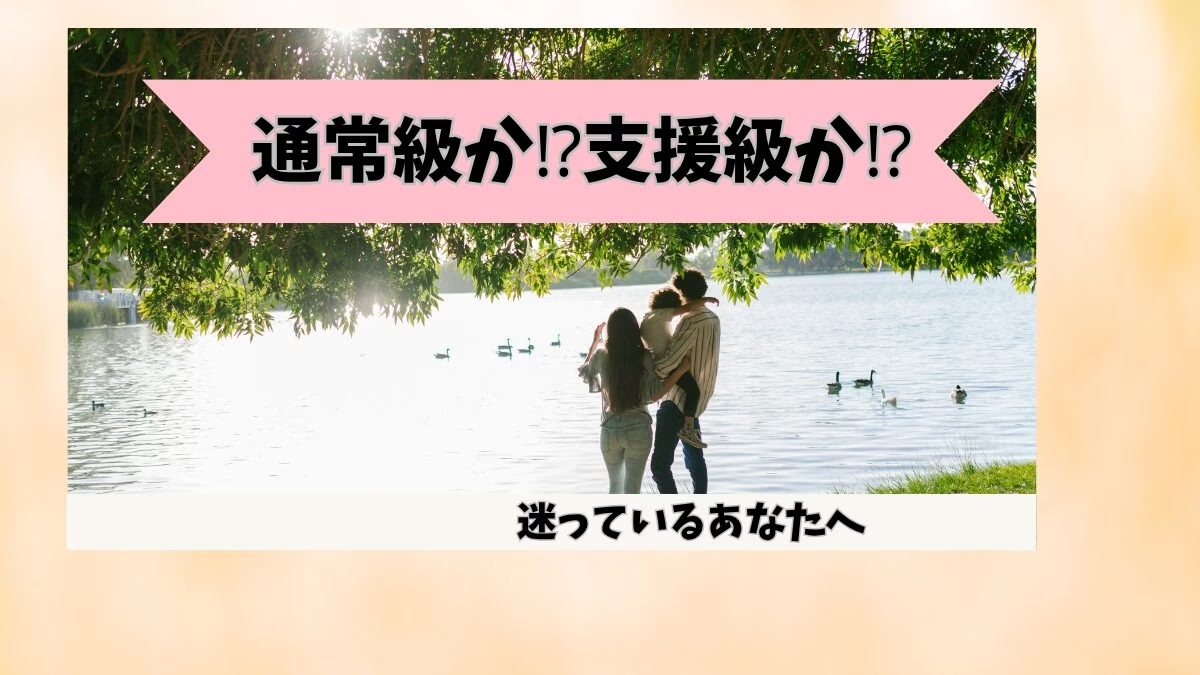


コメント