はじめに

こんにちは。
保育園や小学校の保護者の皆さん、連絡帳を上手に活用していますか?
「もうやってるよ〜」という方もいらっしゃるかもしれません。 でも、ただのやりとりにとどまらず、先生との信頼関係を築くための大事なツールとして活用できているでしょうか?
連絡帳は、活字として残る「記録」です。だからこそ、ちょっとした書き方や伝え方を意識するだけで、先生との距離感がぐっと縮まり、子どもにとってより良い環境づくりにつながります。今回は、担任の先生との信頼性を築くポイントをまとめています。
連絡帳に書くときの基本構成とポイント
連絡帳を書くのが初めてという方も安心してください。以下の流れに沿えば、伝えたいことを無理なくまとめられます。
① 挨拶と日頃の感謝を伝える⭐️
まずは丁寧な挨拶と、先生への感謝の気持ちをひと言。日々子どもを見守ってくださっている先生方に、ねぎらいの言葉は欠かせません。
例:「いつも温かいご指導をありがとうございます。」「いつも大変お世話になっております。」
② 家庭での子どもの様子を簡潔に
最近の家庭での様子や変化があれば、簡単に共有します。園や学校での様子との比較にもなり、先生の気づきにもつながります。あまり長文にならないように簡潔に!
例:「最近はお友達との会話が増え、自信がついてきたようです。」
③ 困りごと・心配ごとを相談する
悩みや心配があるときは、感情的にならず、事実を整理して記載しましょう。トラブルや違和感がある場合は、まとめて伝える方が先生にも伝わりやすいです。
④ 先生の意見を伺う
「こうしてください」と決めつけるのではなく、先生の見解や対応方針を尋ねる姿勢が大切です。
例:「園でのご様子を伺えたらありがたいです。」
⑤ 家庭での対応策・取り組みを書く
家庭でもどう関わっていくかを簡単に記し、先生と連携していく姿勢を見せましょう。
⑥ 最後に改めてお礼
伝えたことに対する感謝を忘れずに。良い印象は次のやりとりにもつながります。
こんなときはどうする?電話連絡のすすめ

小学校などではお迎えの機会がないため、その日のうちに確認したいことは電話で連絡するのも一つの方法です。
「今、先生が忙しかったらどうしよう…」と迷う方もいるかもしれません。でも、緊急性のある内容(ケガや体調不良など)については、先生方も早く知りたいはずです。
連絡帳に書くべきか?電話が良いか?迷ったら、まず自分に問いかけてみると判断しやすくなります。
先生との信頼関係を築くコツ
顔を見せる機会を増やす
時間があるときはお迎え時にひと言でも話す、または保護者活動に参加するなど、先生との関係づくりを日常的に行いましょう。
「協力したい」という姿勢を見せる
お願いばかりでなく、一緒に子どもを支えたいという思いを行動でも伝えることが、信頼関係につながります。
よくあるトラブルを防ぐには?
- 連絡帳を使わず、不満を突然伝える
- ママ友との会話から先生に伝わり、誤解が生まれる
こうしたトラブルを防ぐには、日頃から小まめに記録し、話し合いの姿勢を持つことが大切です。
🌈まとめ|信頼は小さなやりとりから
いかがでしたか?
連絡帳はただの連絡手段ではなく、子どもを取り巻く大人同士がつながる大切なコミュニケーションツールです。
ちょっとした気配りが、先生との関係をより良くし、結果として子どもにとって安心できる環境づくりにつながります。
「干渉しすぎず、でも無関心にならない」
そんなちょうどいい距離感で、子どもの成長を一緒に見守っていきましょう。
✿この記事を書いた人:まる
幼稚園教諭・保育士・放課後児童支援員として、保育に20年以上関わってきた50歳の母です。
家庭では、軽度知的障害のある子どもときょうだい児、2人の子育てに奮闘中。
本ブログでは、障害育児のリアルや暮らしの工夫を発信していますが、自然や植物に触れる時間も大切にしています。植物好きの両親の影響で、季節の庭づくりや草花の記録も時々発信中🌷
今回は、子育てする母親の視点で記事をまとめました。
「同じような境遇の方の心が、少しでもまるくなれば」そんな思いで書いています。障害のある息子を育てながら、日々の支援・工夫・制度利用について情報を発信しています。専門家ではありませんが、同じ悩みを抱える方のヒントになればと願っています。
▶️Instagramもしています。よかったらこちらから覗きにきてください🌱


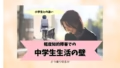
コメント