
「本当に療育手帳を取るべきなのか」「レッテルを貼ることにならないか」
そんな迷いを、私も抱えていました。
我が家は、発達がゆっくりな息子とともに、保育園時代を穏やかに過ごしてきました。
しかし、小学校に上がってから「頑張っているのにできない」息子の姿を見て、支援が必要だと感じるようになりました。
就学後に感じた「見えない困りごと」
小学校入学当初は「このまま普通学級でいけるかもしれない」と期待していました。
ですが、入学後、勉強の遅れや集団行動の難しさが目立ち始めました。
息子は明るく頑張り屋。でも、「わからない」「できない」ことが多く、自信を失っていく様子が見て取れました。
学校側も最初は「様子を見ましょう」というスタンスで、特別支援学級のような制度は使えず。
私自身、「親としてできることは何か?」を考え、まずは発達検査と相談機関への連絡をスタートしました。
療育手帳を取得するまでの流れ

発達外来での検査を経て、児童相談所へ。
一度目の判定では「境界域(グレーゾーン)」とのことで手帳の交付には至りませんでした。
その後、3年生になり、学習面や社会性の差がより明確になってきたことで、再度判定を受けました。
そして、ようやく「療育手帳(C判定)」を取得することができました。
児童相談所というと少し近寄りがたいと感じていました。しかし、母親の話も丁寧に聞き取りしてくださり、息子も安心して検査に取り組むことができました。
家族の中には「レッテルになるのでは?」と心配する声もありましたが、実際には個人のプライバシーがしっかり守られ、自分から話さない限り周囲に知られることもありません。
学校側の反応と「切り札」としての療育手帳
療育手帳を取得したからといって、学校の対応がすぐに変わるわけではありませんでした。
正直なところ、当初は学校側も療育手帳の取得に積極的ではなく、環境が大きく変わったわけではありません。
しかしその後、支援を受ける際の「公式な根拠」として大きな力を発揮してくれました。
就学相談、特別支援学校への入学、さらには将来の就労支援などにもつながる「切り札」になりました。
療育手帳を取得するメリット

実際に取得してみて感じたメリットは、次のとおりです:
- 公的支援がスムーズに受けられる(通級指導、福祉サービスなど)
- 将来の就労支援や進学で有利になる
- 税金の障害者控除などの優遇制度
- 公共施設や交通機関の割引(電車・バス・博物館など)
- 子どもの「困りごと」を説明するための公的な証明になる
「怠けている」「やる気がない」と誤解されがちなグレーゾーンの子どもにとって、客観的な証明としての意味合いも大きいです。
療育手帳のデメリットはある?
個人的に明確なデメリットは感じていません。
ただし、申請や更新の際には、診断書や手続きの負担が多少あります。
また、家族や周囲の理解を得ることに時間がかかる場合もあります。
ですが、それ以上に得られる支援の恩恵は大きく、取得してよかったと今では思えます。
迷っている保護者の方へ伝えたいこと
療育手帳を取得することは「子どもにレッテルを貼ること」ではありません。
むしろ、子どもの未来を広げる選択肢の一つだと、私は感じています。
手帳を持っていることを公表する必要はありませんし、不要になれば返却も可能です。
まずは情報を集めて、信頼できる医師や相談機関と話してみてください。
まとめ|療育手帳は「子どもを守るためのツール」
- 学校だけではフォローしきれない子の「困りごと」を見える化できる
- 将来の進学・就労支援につながる「切り札」になる
- 家族の安心材料としても大きな意味を持つ
今悩んでいる方にとって、私の経験が少しでも参考になれば嬉しいです。
子どものペースで、ゆっくりでいい。一緒に進んでいけたらと思います。
※内容は個人の体験に基づいており、制度の詳細については自治体や医師にご相談ください。
※執筆者プロフィール:障害の息子を育てる母として、日々の支援や社会参加に向けた体験を発信しています。専門家ではありませんが、実体験を通して、同じ悩みを抱える方の力になれたらと願っています。
▶️Instagramもしています。よかったらこちらから覗きにきてください🌱
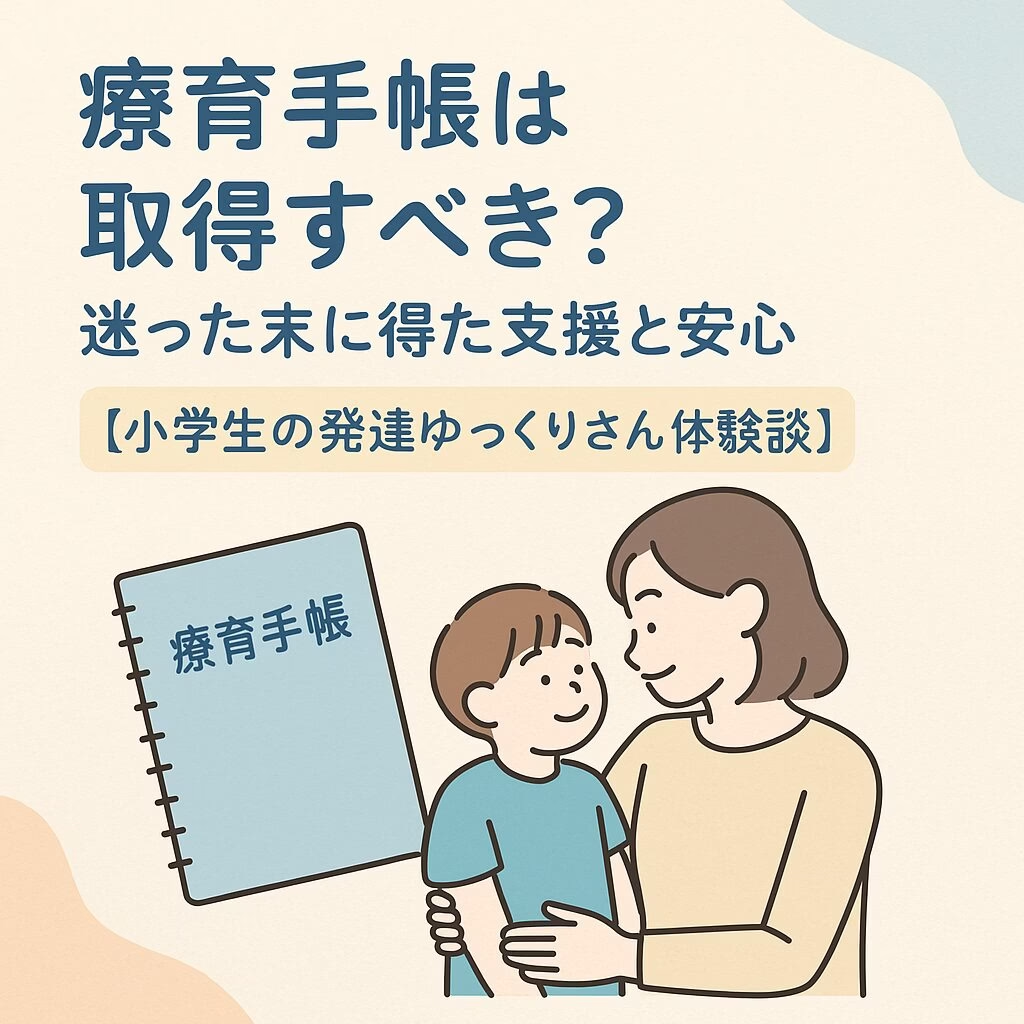

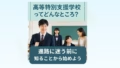
コメント