はじめに

特別支援高等学校に通うことになった息子。初めての支援学校で進学前は不安も多くありましたが、入学後には安心感のある手厚い支援と、きめ細かな教育を受けられました。この記事では、息子の進路選択から就職までの道のり、実習やサポート体制、そして現在の勤務状況について、実体験をもとにご紹介します。
特別支援学校での学びと環境
少人数・手厚い支援体制
息子が通った特別支援高等学校では、1クラス10人以下の少人数体制。担任と副担任がつき、通常級との違いは明らかで、非常に手厚く感じました。
息子は普通級しか経験がなかったため、親子で実際に入学するまで内心ドキドキでした。
社会人としての基礎を学ぶ授業
ビジネスマナーの授業や現場実習の準備など、社会で必要となるスキルを丁寧に教えていただきました。家庭ではなかなか教えられないことも、わかりやすい教科書を使って体系的に学ぶことができました。
この3年間は、将来の就職に向けて動き出す貴重な期間でした。
実践的な成長の機会
自力行動のトレーニング
遠足や修学旅行では、現地集合が基本。中学まで通常級だった息子にとっても大きな挑戦でしたが、電車移動の練習を積み重ねていたことで、自信にもつながりました。
実習や就職へ向けての準備段階として自然と行動力が上がるよう設定されているな、と感じました。
文部科学省 学習指導要領「生きる力」|特別支援学校高等部学習指導要領 第6章 自立活動について
職業への理解を深める
職業の下調べやお礼状の書き方、現場実習などを通して、自分に合った職種について少しずつ理解を深めていきました。
これまでの学力を伸ばすための授業より、こうした実践的な学習の方が多かったです。
就職活動のサポート体制
担任+企業開拓の専任教員が担当
進路相談では、担任だけでなく、企業とのパイプを持つ専門の先生がサポートしてくれました。希望の地域や業種を伝えると、企業への問い合わせまでしてくださり、本当にきめ細かな対応でした。
実習で見えた「向き・不向き」
一般企業での実習体験

一般企業の障害者雇用枠での実習では、洗車、掃除、組み立て補助などの業務を体験。障害のない方々と同じ環境で働く中で孤立感も感じたようでした。更に正社員への道がある企業もありましたが、求められる作業に苦戦していました。実習後には疲れ果ててしまい、継続は難しいと判断しました。
業務内容が得意な場合は向いている環境だと思います。企業と個人が就職前にお互いに確認できる実習はとても重要でした。
特例子会社での実習体験
同じような境遇の方と働くことのできる特例子会社。息子の実習先では会社の中で複数の職種を体験でき、自分に合った仕事を見つけることができました。スタッフの方の支援もあり、安心して仕事に取り組むことができたようです。
🧩 特例子会社とは?
大手企業が設立した、障害者雇用のための特別な会社。多様な職種が用意され、支援体制も整っており、安心して働ける環境です。
勤務形態と定着までの道のり
勤務開始は6時間の契約雇用から。半年ごとの更新を経て、現在は8時間勤務で有期雇用ではなくなりました。最初の頃は、いつ辞めることになるか不安でいっぱいでしたが、5年目にしてようやく安定してきました。
卒業後の支援体制
就職後も、しばらくは学校の先生が会社を訪問して状況を確認し、必要に応じてサポートを続けてくれました。その後は、地域の訓練センターの担当者に引き継ぎ。問題が起きたときにはすぐに間に入ってくれ、精神的にも大きな支えとなりました。
「サポートを受ける強さ」を知って
息子が精神的に追い込まれた時期には、円形脱毛症が現れることもありました。それでも会社と学校、家庭の連携で乗り越えることができました。
主治医の「この先、本当にサポートなしで生きていくのね」という言葉の重みを、今になって実感します。サポートを拒むのではなく、感謝して受け入れながら、自分の力を発揮する道を応援していきたいと感じています。
現在の生活とヘルプマーク

通勤中に倒れてしまいそうになったこともあり、ヘルプマークを携帯しています。
「普通の判断」が難しい瞬間は、今もあります。
本人も努力していますが、外部の理解と支援は不可欠です。
🚨 ヘルプマークについて詳しくはこちらの記事で:中学卒業後の進路に迷う親へ|軽度知的障害の息子が特別支援高校を選ぶまで|ヘルプマークの活用も
おわりに
特別支援高等学校という選択は、我が家にとって正解でした。
「支援を受けながら働く」という生き方を、もっと多くの方に知ってほしいと思い、この記事をまとめました。
サポートを拒否することが強さではなく、サポートに感謝して精一杯生きることを応援したいと考えています。
🔎 参考リンク
🧾注意事項
※本記事は一個人の体験談に基づいています。制度や支援内容は地域・年度によって異なります。必ず最新情報を自治体や関係機関でご確認ください。
執筆者プロフィール
障害のある息子を育てながら、日々の支援・工夫・制度利用について情報を発信しています。専門家ではありませんが、同じ悩みを抱える方のヒントになればと願っています。
関連記事✨
【体験談】軽度知的障害の息子が1泊2日のグループホームへ!自立への第一歩
[障害福祉サービス受給者証]とは?グループホーム利用の第一歩|軽度知的障害の息子の場合
【グレーゾーンでも申請OK?】療育手帳と特別児童扶養手当・放課後等デイサービスまで
中学卒業後の進路に迷う親へ|軽度知的障害の息子が特別支援高校を選ぶまで
▶️Instagramもしています。よかったらこちらから覗きにきてください🌱
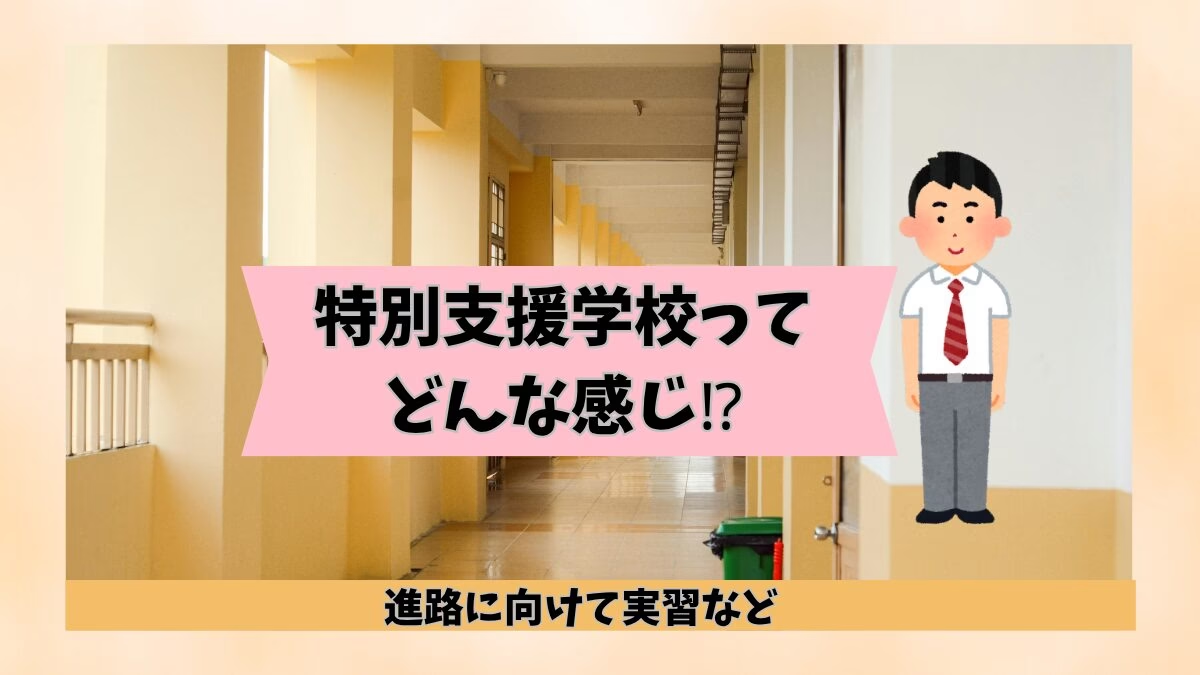
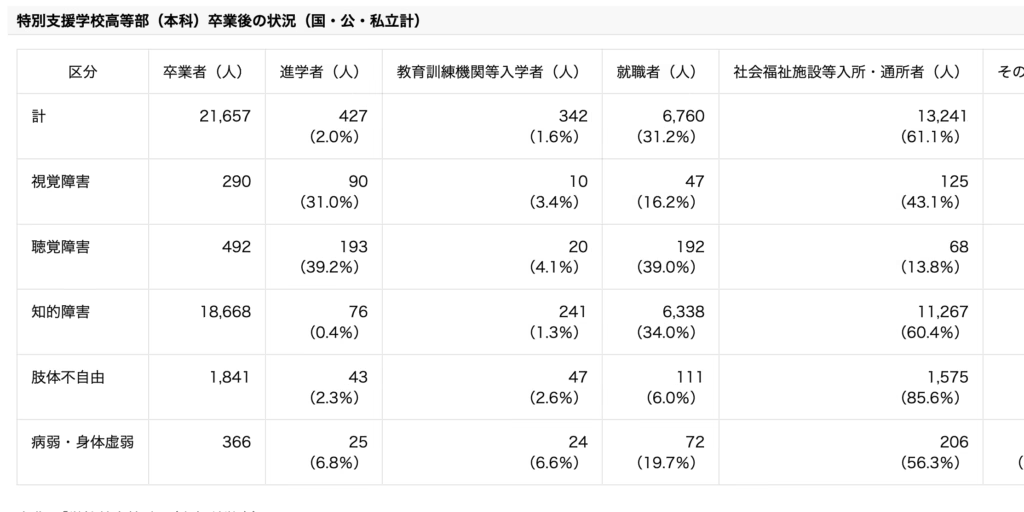

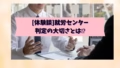
コメント