はじめに

こんにちは、まるです!
今回は、障害者雇用枠での就職活動を行う上で、私たち親子にとってとても重要だった制度について、実体験をもとにご紹介したいと思います。
息子のプロフィール
息子は軽度知的障害と**自閉症スペクトラム(ASD)**ADHD(注意欠陥)を併せ持ち、中学までは通常学級でしたが、特別支援高等学校に進学しました。学校生活の中で、いくつかの実習を重ねることで、現在の就労先と出会うことができました。
でも、そこにたどり着くまでには、いくつかの重要な制度を利用する必要があったのです。
特別支援高等学校への進学と療育手帳の取得
特別支援高等学校に入学するには、学科試験や面接などの選考がありました。通常クラスからの支援学校への変更だったので、資料や受験についてなど学校も情報が不足している状況でした。そこで、自分で調べて中学校へは報告をしていくスタイルでした。
まず、前提として、療育手帳の取得が必要条件となっていました。療育手帳を取得していない場合は、別の障害証明書が必要だったと思います。基本的には入学後皆さんが取得していました。
就職に向けた大きな支援:障害者職業センター
進路指導の中で、特別支援学校の先生から紹介されたのが、障害者職業センターでした。
ここでは、次のような支援が受けられます:
- 就職に向けての相談
- 職業能力の評価
- 就職前後の支援(職場定着支援や職場復帰支援 など)
🔑キーポイント:職業能力評価での「重度知的障害者判定」

その中でも、特に大きな影響を与えたのが、職業能力評価での「重度知的障害者判定」でした。
最初は「重度」という言葉に戸惑いもありましたが、先生からの説明で納得できました。
この判定を受けることで、企業側は障害者雇用率制度の枠として「2名分の雇用」にカウントされるそうです。
厚生労働省障害者雇用率制度についてはこちら
普通高校では得られなかったこうした情報を、特別支援学校では丁寧に教えていただけたことは本当にありがたかったです。
就職後の見守り体制
卒業後は、自宅近くの**就労支援センター(NPO法人)**を学校が紹介してくれました。
現在も、就職先企業との関係性をサポートしてくださっており、
- 定期的な保護者への電話連絡
- 息子への「何かあったらいつでもおいでね」という温かい声かけ
といった形で、継続的な支援をいただいています。
障害者雇用を目指す方へ伝えたいこと
障害者雇用を目指す場合、必要な情報を調べても、自分たちの家庭に合っているのか判断が難しいと感じることが多々ありました。
でも、こうした制度や支援の存在があったからこそ、息子が安心して働きながら生活できているのだと思います。情報を探すことは簡単ではありませでしたが、ぜひ将来のために行動をすると安心への糸口につながるかもしれません。応援しています。たくさんの制度や支援が整っていると思います。心から応援しています。
明日も楽しく・心まるく過ごせますように♪
🧾注意事項
※本記事は一個人の体験談に基づいています。制度や支援内容は地域・年度によって異なります。必ず最新情報を自治体や関係機関でご確認ください。
執筆者プロフィール
障害のある息子を育てながら、日々の支援・工夫・制度利用について情報を発信しています。専門家ではありませんが、同じ悩みを抱える方のヒントになればと願っています。
関連記事✨
特別支援高等学校に通った息子の進路と就職までの道のり【実体験レポート】

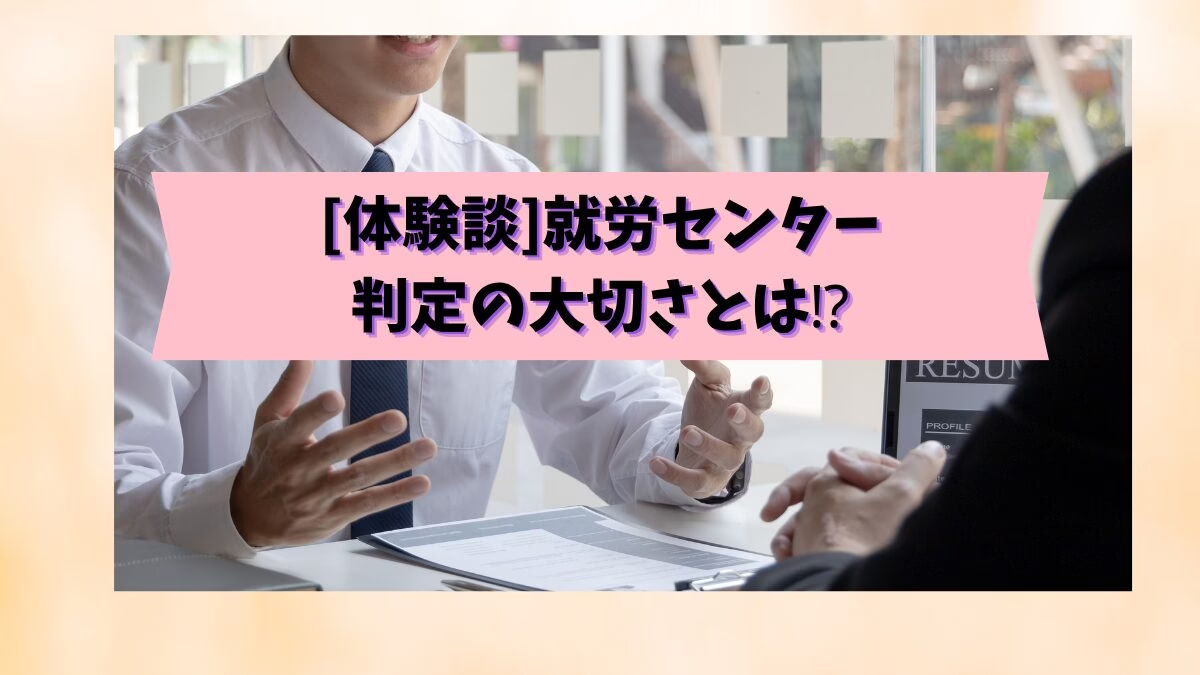
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/47f0ac79.2d5de24c.47f0ac7a.83418ab8/?me_id=1358201&item_id=10164046&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Firisplaza-r%2Fcabinet%2F10076930%2Fimgrc0110488524.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)



コメント