はじめに

「この子の未来に、光はあるのだろうか」
「何をすればいいのかわからない」
「そばにいてあげることが正解なの?」
そんな不安と戸惑いの中で子育てをしてきた私が、今ならあの頃の自分に伝えたい言葉があります。
「まずは落ち着いて。焦らず、この子を見つめてあげて」
この記事では、私自身の経験から「診断後に何をすべきか」を段階的にまとめました。
保育園入所と仕事復帰|社会とのつながりが支えになった
診断当時、医師から「子ども同士の関わりがとても大切」と助言を受けました。
それをきっかけに、保育園への入所と、仕事への復帰を決意。
夫は多忙だったため、実家に頼りながら育児と仕事を両立しました。
保育士として復職してからは、他の保護者の悩みにも共感できるようになり、社会とつながることの大切さを実感しました。
祖父母の「大人が3人いても仕方ないでしょ(笑)」という言葉にも救われ、気持ちが楽になりました。
小学校で感じた違和感と、診断までの流れ
息子が通った小学校には特別支援学級がなく、「普通学級で皆で見ていきましょう」と言われました。
けれど、頑張っても進まない学習に違和感を覚え、NICU時代からお世話になっていた病院へ相談。
検査の結果、「軽度知的障害」の診断を受けました。
息子の前でしたが、涙が止まりませんでした。
安堵と不安が交錯する瞬間でした。
診断後に私が行った3つのステップ

- ① 息子の“得意”と“苦手”を見つける 得意なこと:
- 文字や形の認識
- 人との関わりが好き
- 話すことが得意
- 乗り物が好き
- 抽象的な指示が理解しづらい
- 数量や時間感覚が曖昧
- 体力・体幹が弱い
- トイレトレーニングの遅れ
- ② 児童相談所に相談する 1年生のときに児童相談所へ相談。
最初は「グレーゾーン」として様子見でしたが、3年生になる頃には差がはっきり。
再診断により「療育手帳(C判定)」を取得できました。 母親として「困っていること」を正しく伝える重要性を学びました。
支援を引き出すためには「母の伝える力」が必要です。 - ③ 療育手帳を取得する 家族から「レッテルになるのでは?」という不安の声もありました。
でも、療育手帳を取得したことで、教育・支援・将来の就労の選択肢が広がりました。 プライバシーは守られ、周囲に知られることもありませんでした。
必要なくなった場合は返却も可能です。
療育手帳とは?取得のメリットと将来への影響

療育手帳(自治体により「愛の手帳」など名称は異なります)は、知的障害がある人の支援のための公的証明です。
息子はその後、特別支援高等学校へ進学し、障害者雇用枠での就職へとつながりました。
療育手帳は「将来の切り札」となりました。
療育手帳の取得メリット
- 障害者控除などの税制優遇
- 公共・民間施設の割引(電車・バス・博物館など)
取得後は、公園・図書館・音楽イベントなどにも気軽に出かけるようになりました。
「やる気がない」と誤解されやすい息子にとって、公的証明が支援の幅を広げる武器になったのです。
取得のデメリットは?
私の体験では明確なデメリットはありませんでした。
ただし、申請・更新に一定の手間がかかることは事実です。
精神障害者保健福祉手帳との違い
発達障害を持つ方がすべて療育手帳を取得できるとは限りません。
知的障害がない場合は、精神障害者保健福祉手帳の対象となるケースもあります。 どの手帳を申請すべきか迷ったら、自治体の福祉課や医師に相談するのが安心です。
【まとめ】
診断を受けたあとに、親としてできること
- 子どもの「得意」と「困りごと」を整理する
- 児童相談所や医療機関、学校へ相談する
- 療育手帳や支援制度の活用を検討する
- 小さな日記や記録が支援申請の助けになる ので継続を
- ママの笑顔が、子どもにとっての最大の安心材料 にも
今、同じように悩んでいる方へ。
「できないこと」は、未来への伸びしろです。
あなたの笑顔が、子どもの心を支える力になります。一人で悩ま内容にしてください。
※この記事は個人の経験に基づいています。各制度の詳細については自治体・医師・専門機関にご相談ください。 関連記事:発達グレーゾーンでも受けられた!療育手帳・特別児童扶養手当・放課後等デイサービスの支援体験まとめ
関連記事
- 他人からの一言で救われた経験と傷ついた経験|軽度知的障害の息子と歩んできた23年
- 妹と兄のケンカと仲直りのパターン集|軽度知的障害の兄と健常児の妹の関係から学んだこと
- 軽度知的障害の息子が初めて一人で買い物できた日|親がした準備と気づき
- 高等特別支援学校ってどんなところ?通ってわかった実際の様子と学び【体験談】見学時のチェックポイント付き💡
- 【体験談】療育手帳の取得に迷っている方へ|わが家の決断と感じたメリット・デメリット
▶️Instagramもしています。よかったらこちらから覗きにきてください🌱
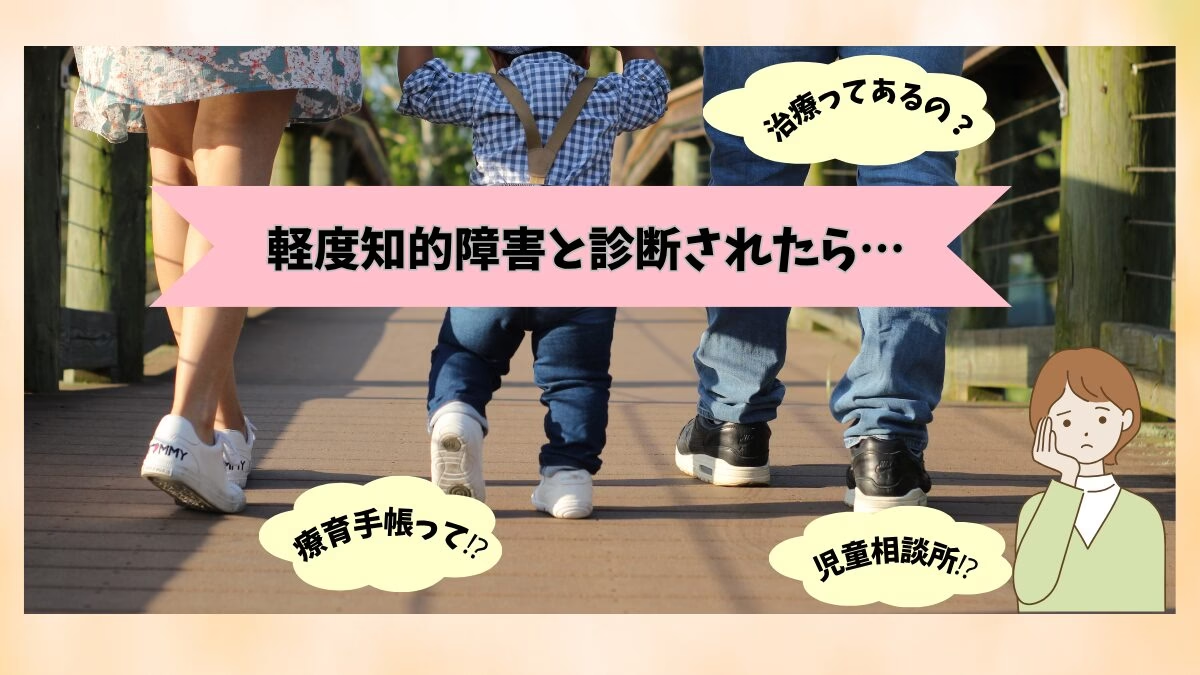


コメント